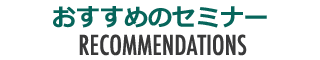■会場受講 ■ライブ配信 ■アーカイブ配信
【内閣官房/内閣府/警察庁/総務省/国交省/経産省/トヨタ/ホンダ】


9月 1日(水) 終了済
内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 参事官補佐
森 健悟(もり けんご) 氏
「官民ITS構想・ロードマップ」は、我が国のITS・自動運転に係る戦略を記載した文書として2014年6月に策定されて以降毎年改定を行っており、2021年6月にIT総合戦略本部において最新版が決定された。講演では主なポイントについて説明する。
1.はじめに
2.これまでの取組と実績
3.今後のITS構想の基本的考え方
4.質疑応答/名刺交換
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
新世代移動通信システム推進室 課長補佐
江原 真一郎(えばら しんいちろう) 氏
交通事故削減・渋滞緩和、移動弱者支援や快適な移動空間の実現等、自動運転に対する社会の期待が高まっている。本講義では、通信行政を担う総務省の立場から、自動運転社会の実現に向けた総務省の取組を国際動向をまじえながらご紹介する。また、2020年から商用サービスが開始された5Gの現状について触れつつ、5G時代の自動運転の姿を展望する。
1.5.9GHz帯V2X用通信システムに関する検討状況
2.ITS用無線通信における国際的な動き
3.自動運転に必要な通信要件の検討状況
4.交通信号機を活用した5Gネットワークの構築の検討状況
5.質疑応答/名刺交換
国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課
課長補佐
石川 雄基(いしかわ ゆうき) 氏
国土交通省では、新たなモビリティサービスであるMaaS(Mobility as a Service)について、「日本版MaaS推進・支援事業」を中心とした取組みを行っている。本公演では、国土交通省によるMaaSへのアプローチや、コロナ禍におけるMaaSの役割、今後の取組等について紹介する。
1.地域公共交通の現状と課題
2.MaaS(Mobility as a Service)について
3.国土交通省のアプローチ
4.With/Afterコロナ時代におけるMaaS
5.質疑応答/名刺交換
警察庁 交通局交通企画課 専門官
大橋 雅也(おおはし まさや) 氏
自動運転技術は交通事故の削減、渋滞の緩和等を図る上で有用と考えられることから、警察では、我が国の道路環境に応じた自動運転が早期に実現されるよう、交通関連法規の見直し、実証実験の環境整備、技術開発等を推進している。
本講演では、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の枠組みを活用した警察庁における技術開発について紹介する。
1.日本における交通事故の発生状況
2.自動運転の実現に向けた警察庁の取組
3.信号情報の提供等に関する技術開発
4.質疑応答/名刺交換
経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐
山本 誠一朗(やまもと せいいちろう) 氏
いわゆる「CASE」と言われる百年に一度の技術変革の中で、自動車産業は大きく産業構造の転換を求められている。他方で、先進的な技術やサービスの社会実装を通じ、モータリゼーションや少子高齢化に伴い進行してきた社会課題の解決も期待されている。本講演では、そうした将来のモビリティ社会像の展望や、それに向けたMaaSや自動運転分野での経済産業省の取組を紹介する。
1.自動車産業の構造変化
2.将来のモビリティ社会像
3.経済産業省の取組(MaaS、自動運転)
4.質疑応答/名刺交換
トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー
自動運転モビリティ イノベーション担当
兼 自動運転・先進安全統括部主査
ウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社
Automated Driving Strategy and Mapping Vice President
Mandali Khalesi(まんだり かれしー) 氏
安全な先進運転支援技術や自動運転には高精度で最新の地図が必要です。低コスト、高精度、高頻度で地図の生成・更新ができる自動地図生成プラットフォーム(Automated Mapping Platform、AMP)では、従来使われている地図情報の精度や更新頻度の課題を解決し、商用車の安全性の向上をめざしています。オープンなプラットフォームとして様々なパートナーと協業することで、更なる価値を提供していきます。
1.先進運転支援技術・自動運転における高精度地図の重要性
2.従来の地図を用いた技術の課題
3.AMPのベネフィット
4.オープンなプラットフォームとしてのパートナーとの協業
5.質疑応答/名刺交換
株式会社本田技術研究所 先進技術研究所
AD/ADAS研究開発室 エグゼクティブチーフエンジニア
波多野 邦道(はたの くにみち) 氏
2020年日本は世界で初めてレベル3自動運転に対応した法整備を完了し、高速道路などの限定エリアでの自動運転の実用化が可能となった。本講演は高速道路上でのレベル3自動運転の基本的な技術と実用化の取り組みを概説する。
1.日本の自動運転実用化に向けた取り組み概要
2.ホンダの自動運転/安全運転支援の取り組み
3.自動運転を実用化するための要素技術
4.自動運転の安全性を担保する取り組み
5.質疑応答/名刺交換
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局
参事官(社会システム基盤)付
SIP自動運転担当 上席政策調査員
荒木 雄一(あらき ゆういち) 氏
SIP自動運転では、自動運転の実用化に向けて、地図やインフラなど自動運転に必要な協調領域の研究開発等を産学官連携で推進している。ダイナミックマップに紐づける交通環境情報の構築と配信の実現に向けた技術開発や東京臨海部での実証実験を始め、安全性評価環境の構築やセキュリティ、社会的受容性の醸成等の取組について紹介する。
1.交通環境情報の構築と配信
2.東京臨海部実証実験
3.仮想空間における安全性評価環境の構築、サイバーセキュリティ
4.地理系データの流通ポータルの構築
5.社会的受容性の醸成、国際連携の強化
6.質疑応答/名刺交換


自動車メーカーにてITSの普及に向けた業務に従事。2020年1月 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 入省。現在に至る。

2008年 総務省入省以来、4Gの国際標準化、地デジ日本方式の海外展開、消防救急無線のデジタル化等の業務に従事。2019年7月より総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室のITS担当に着任し、現在に至る。

2013年 入省。2016年7月 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課企画係長。2018年7月 近畿地方整備局建政部計画管理課長。2019年7月 近畿地方整備局総務部人事課長。2020年7月 現職。
2014年、警察庁に入庁。警察庁情報通信局情報管理課、警察庁長官官房総務課、警察庁情報通信局情報通信企画課を経て、2021年1月より現職。UTMS(Universal Traffic Management Systems)や自動運転に関する技術企画を担当。

2016年、経済産業省に入省。資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課、経済産業省経済産業政策局企業行動課を経て、2020年7月より現職。CASE分野、とりわけ自動運転・MaaSに関する企画立案を担当。

ウーブン・プラネット・ホールディングスで自動運転戦略・製品アライアンス・マッピングシステムを担う自動運転事業のVice Presidentを務める。トヨタ自動車の先進技術開発カンパニーにて自動運転モビリティ、イノベーション担当と自動運転・先進安全統括部主査を兼任。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン大学院にて宇宙物理学修士号を取得。1999年から日本にて地方自治体やソフトウェア企業のIT業務を経験、2008年より欧州にてTomTom NV、Binatone Telecom PLC、Nokiaなど最先端IT企業で位置情報連動型ソフトウェア開発に携わる。2014年にNokiaのHEREにてアジア・パシフィック市場向けオートモーティブ製品事業統括に就任。ITS Japan自動運転研究会の自動運転支援センターワーキング・グループ前リーダーとして、首都圏以外の地域社会に貢献する自動運転モビリティ開発支援を担当。

1990年 株式会社本田技術研究所に入社、電装研究開発部門に所属しシャシ制御システムのECU開発に従事。2009年よりシャシ開発部門にて電動サーボブレーキの実用化に従事。2015年「電動サーボブレーキシステムの開発」にて第65回自動車技術会技術開発賞受賞。2013年より自動運転の研究開発に取り組み、2020年11月世界初のレベル3自動運転の型式指定を取得。2021年4月より自工会 自動運転部会の部会長。

1993年4月 日本信号株式会社入社。主に交通管制システムや交通信号制御機等の設計・開発を担当。2019年より協調型自動運転に関連する製品の設計・開発を担当。2020年10月 内閣府SIP自動運転担当に着任し、現在に至る。